2023.7.21 お知らせ
富山県富山市に少人数単発ワークショップのみの
ものづくりスペースをオープン準備中
教室名や内容を変更して新たにスタートします。
最新の情報はインスタにて公開予定です。
単発ワークショップ開催の際は下記、
ピテコ公式ラインにて参加者を募集いたします。
ご興味ありましたらぜひ登録お願いいたします。

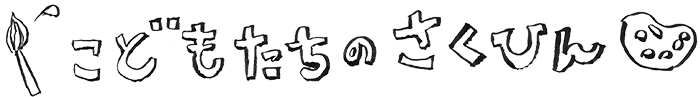




■他 過去作品は……


神奈川県川崎市「ぞうのいえ」の子供たちの作品をインスタグラムでご覧いただけます
ぞうのいえ(https://www.instagram.com/zounoie)